買い物リストは、一見シンプルなようでいて、実は「時間」と「お金」のムダを減らすための重要なツールです。
なんとなくメモして買い物に行くと、同じ物を重複して買ったり、必要な物を買い忘れたりといったことが起こりがちです。
今回は、無駄なく、スムーズに買い物ができる「買い物リストの作り方」を、手順に沿って具体的に紹介します。
買い物リストの目的をはっきりさせる

まず最初に決めるべきは、「どんな目的の買い物リストを作るのか」という点です。
買い物には大きく分けて、次の3種類があります。
-
日常の消耗品リスト(例:トイレットペーパー、洗剤、ラップなど)
-
食材リスト(例:週末のまとめ買い、作り置き用の食材など)
-
特別な目的の買い物リスト(例:新生活準備、季節の入れ替え、掃除道具の補充など)
この目的があいまいだと、リストが長くなりすぎて使いづらくなります。
例えば「日用品」と「季節の入れ替え用品」が混在していると、店舗を回る順番がバラバラになり、時間がかかります。
まずは買い物の目的をひとつに絞ってリストを作ることが、迷わない第一歩です。
まずは「定位置」を見直して在庫を確認する

リストを作る前にやるべきことは、家の中の在庫確認です。
特に消耗品の場合、「まだある」と思っていたのに切らしていたり、逆に「買ったばかりなのにまた買ってしまう」ことが多くあります。
確認のコツは、「定位置を決めて、そこだけ見る」ことです。
たとえば、
-
洗剤・スポンジ → 洗面所下の収納
-
トイレットペーパー → トイレ上段棚
-
ラップ・袋類 → キッチン引き出し右側
このようにモノの置き場を固定しておくと、在庫確認が短時間で終わります。
買い物リスト作成の効率を上げるために、「どこを見れば在庫がわかるか」を明確にしておくことが重要です。
リストは「使う場所」ごとに分けて書く
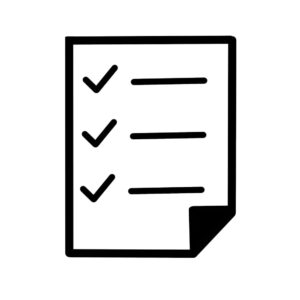
買い物リストを作るとき、多くの人は「必要な順」や「思いついた順」に書いてしまいがちです。
しかし、それでは店内での移動が増え、時間も手間もかかります。
効率的なのは、使う場所ごとに分類して書く方法です。
例として、以下のように分けておくと分かりやすいです。
| 分類 | 例 |
|---|---|
| キッチン用品 | ラップ、キッチンペーパー、食器用洗剤 |
| バス・トイレ用品 | トイレットペーパー、シャンプー、掃除シート |
| 掃除用品 | クイックルワイパー、雑巾、ゴミ袋 |
| 収納用品 | 仕切りトレー、ファイルボックス、S字フック |
この分類を「使う場所」で行うと、片づけの習慣にもつながります。
家の中のどこで何を使うかが整理されていれば、買い物後の収納もスムーズです。
リスト作成は「紙+デジタルの併用」が最も便利

買い物リストの形式には、主に次の3種類があります。
-
紙のメモ(ノート・付箋など)
-
スマホのメモアプリ
-
専用の買い物リストアプリ
それぞれに利点がありますが、最も使いやすいのは**「紙+スマホ」併用型**です。
家では紙で確認しながら書き出し、外出時はスマホに転記するだけで済みます。
例えば、冷蔵庫に貼ったホワイトボードやメモ紙に家族が書き込んでおき、買い物前にスマホアプリに入力して出かける。
この方法なら、書き忘れを防ぎつつ、店内でも両手が自由に使えます。
また、Google KeepやLINEメモなど、複数人で共有できるアプリを使うと、
家族の誰かが「これ買っておいて」と追加できるので便利です。
買い物リストは「定型化」して時短を狙う

毎回ゼロからリストを作るのは非効率です。
そこでおすすめなのが、「定型リスト」を作っておくことです。
定型リストとは、常に確認が必要な定番アイテムをまとめたテンプレートです。
次のような形で、Excelやメモアプリに一覧化しておくと便利です。
| カテゴリ | 品名 | チェック欄 |
|---|---|---|
| キッチン | 食器用洗剤 | □ |
| キッチン | キッチンペーパー | □ |
| バス・トイレ | トイレットペーパー | □ |
| バス・トイレ | ボディソープ | □ |
| 掃除用品 | ゴミ袋 | □ |
買い物前にこのリストを見て、必要な箇所だけチェックを入れるだけで済みます。
一度作っておけば、次回以降の買い物準備が格段に速くなります。
さらに応用として、「1か月に1回チェック」「週1で補充確認」などの頻度を決めると、無駄な買い物が減ります。
店舗別に並び替えるとさらにスムーズ

スーパーやドラッグストア、ホームセンターなど、行く店舗が決まっている場合は、
店舗ごとに並び順をリストに反映させるのが有効です。
たとえば、スーパーの場合:
-
入り口すぐ:野菜・果物コーナー
-
中央通路:調味料・乾物
-
奥:冷凍食品・乳製品
-
出口付近:日用品コーナー
この順番にリストを並べ替えておくと、店内での「戻り買い」がなくなります。
一度ルートを意識してリストを作ってみると、買い物時間が30%ほど短縮されるという結果もあります。
また、複数店舗を回る場合は、「どこで何を買うか」を事前に振り分けておきましょう。
たとえば、洗剤類はドラッグストア、収納用品はホームセンターなど。
同じ物でも店舗によって価格差があるため、リストに「どの店で買うか」をメモしておくと出費管理にもなります。
買い物後の「補充」と「記録」で次につなげる

買い物が終わっても、そこでリストを終わりにしないのがポイントです。
次回の効率を上げるために、買い物後の記録と補充をしておきます。
手順は以下の通りです。
-
買ったものを種類ごとにまとめて置く(キッチン用品、洗面用品など)
-
使う場所に戻しながら、古いものが残っていないか確認する
-
リストに「次回補充が必要なもの」をメモしておく
たとえば、ストックがあと1つになった段階で「次回要購入」とメモしておくと、
買い忘れを防げます。
また、価格をメモしておくと、次に買うときの比較材料になります。
「いつも買う店では○円」「他店では△円」と記録しておけば、無駄な出費を防げます。
まとめ:買い物リストは“段取り表”と考える

買い物リストは単なるメモではなく、家の中の管理表・段取り表のような役割を持っています。
在庫を確認し、使う場所を意識し、定型化していくことで、
家事の流れ全体がスムーズになります。
リスト作りを習慣化すると、「あれがない」「買いすぎた」というストレスが減り、
家の中が整いやすくなります。
時間もお金もムダにしないために、今日から実践できる買い物リストの仕組みを整えてみてください。


